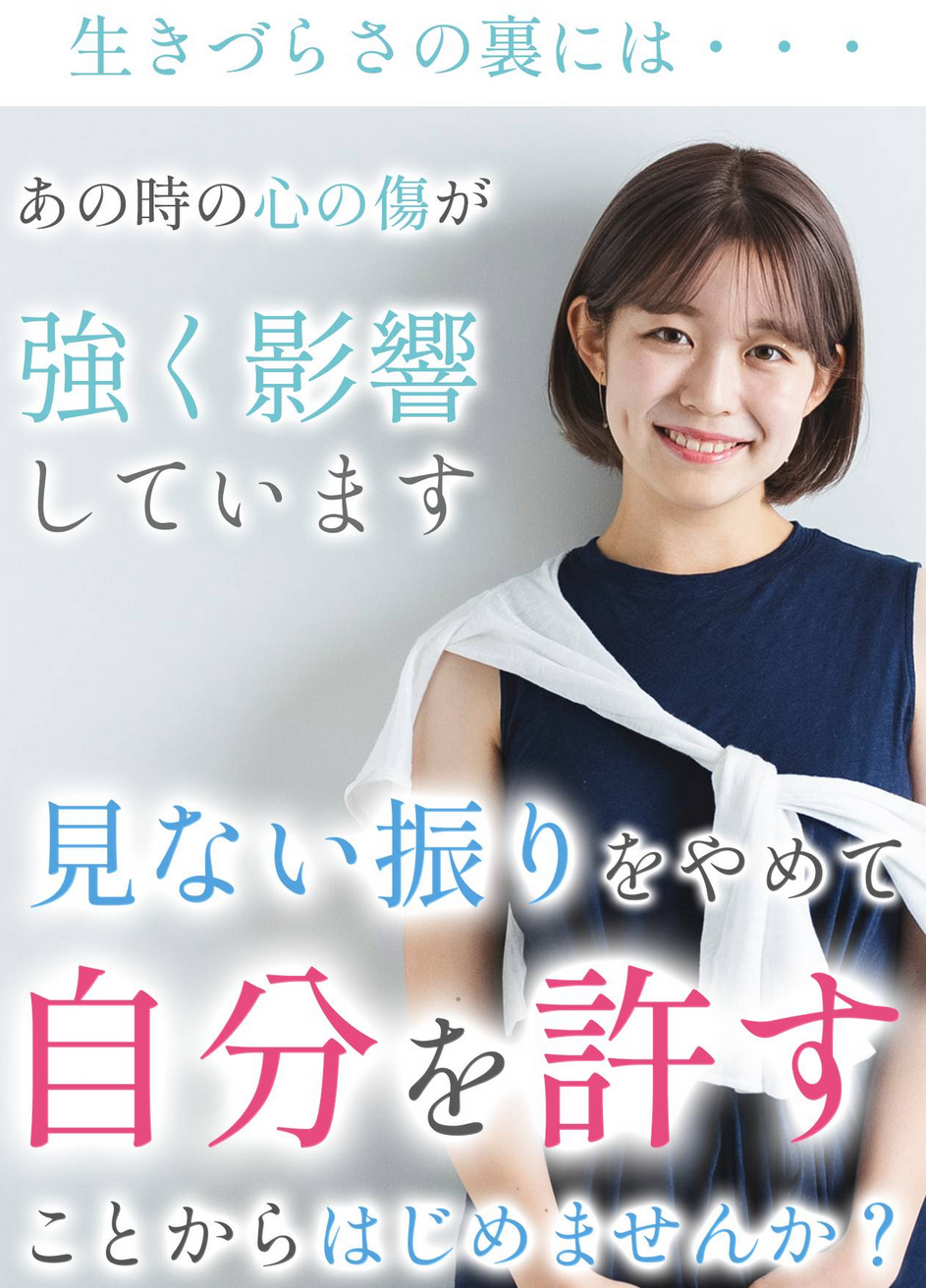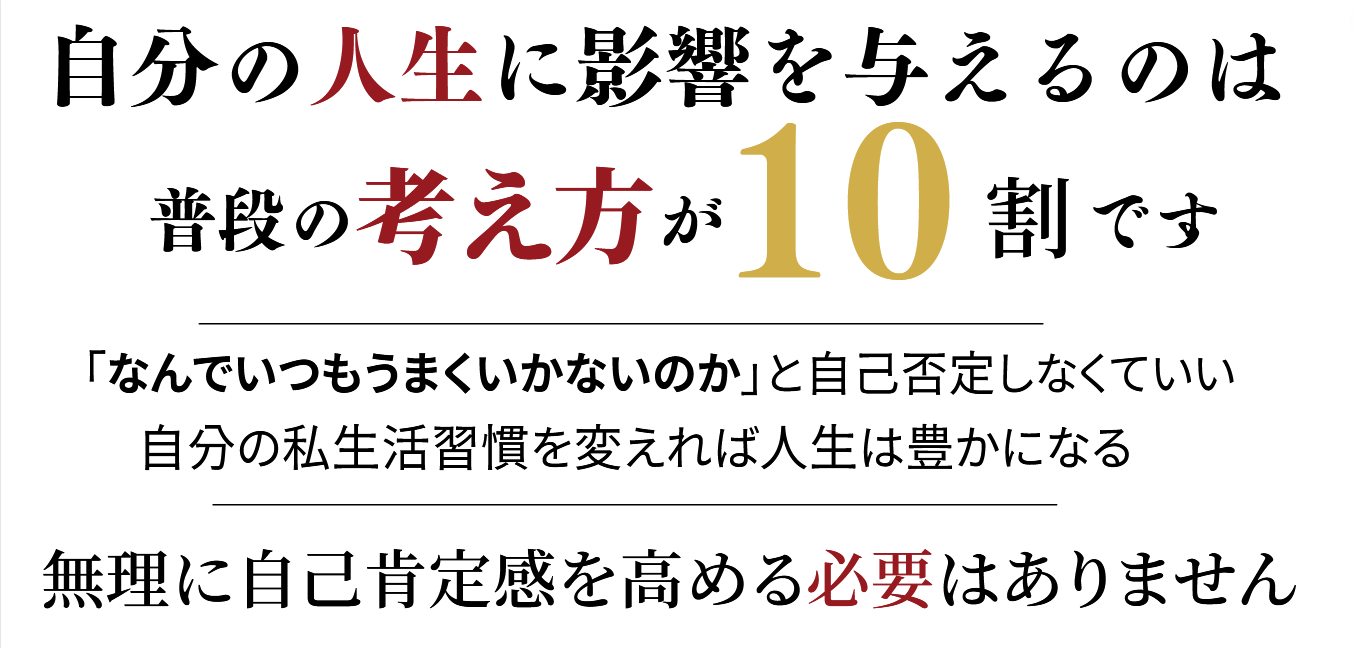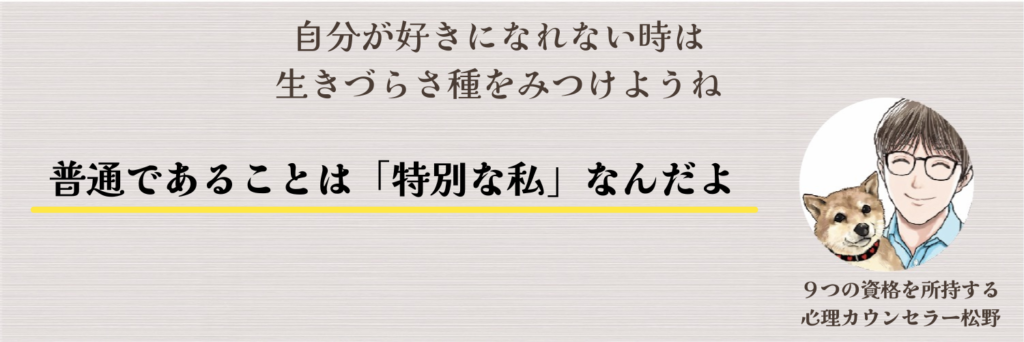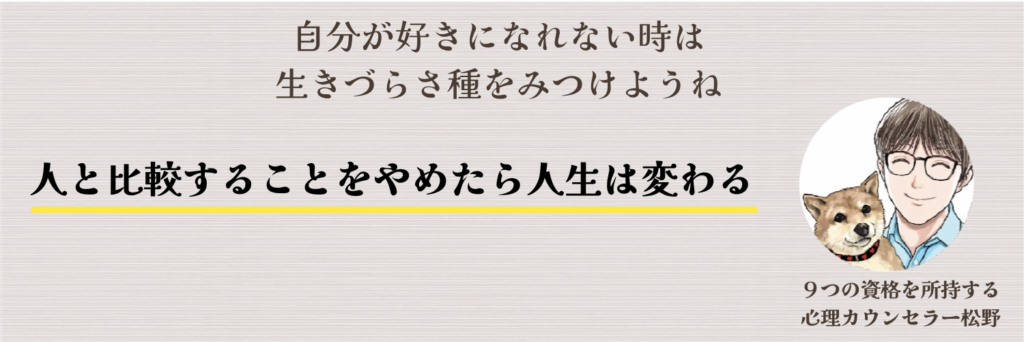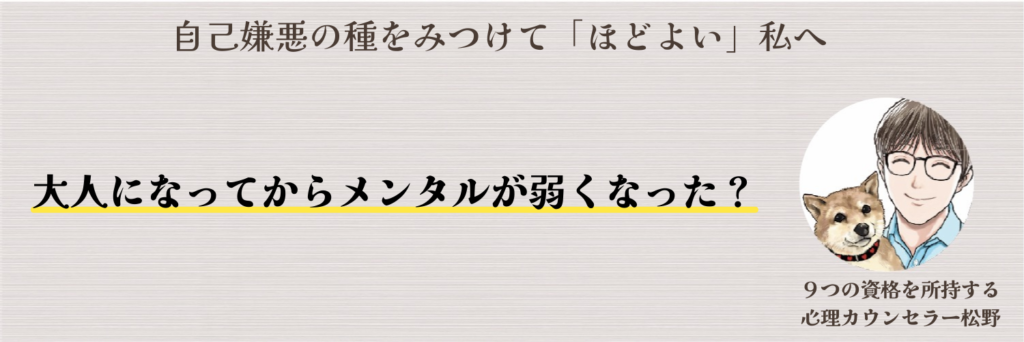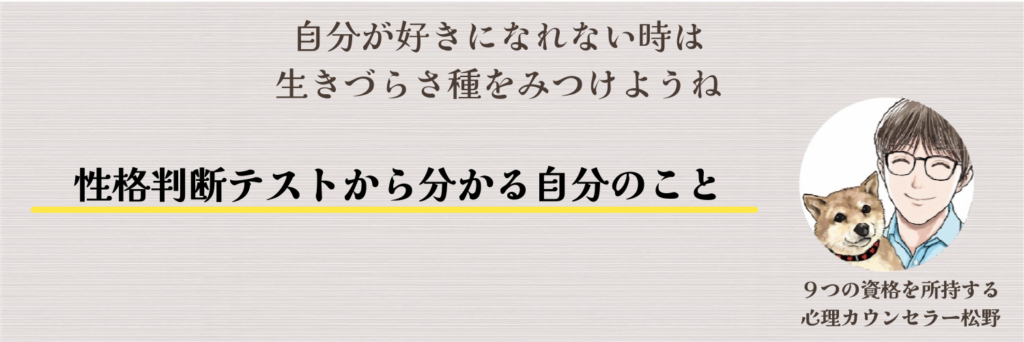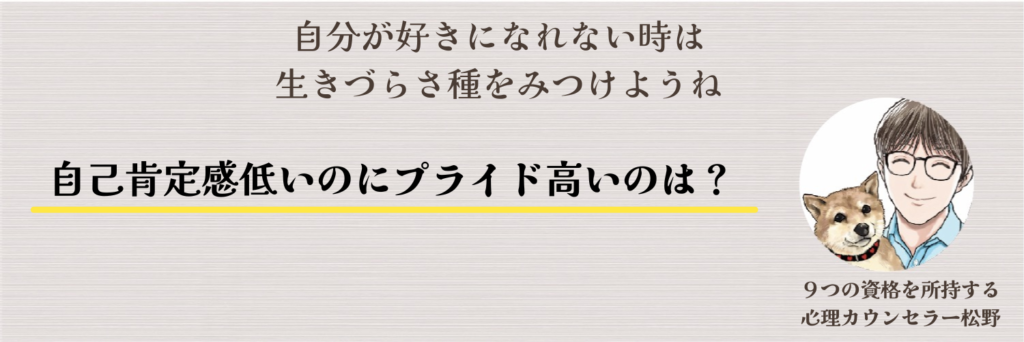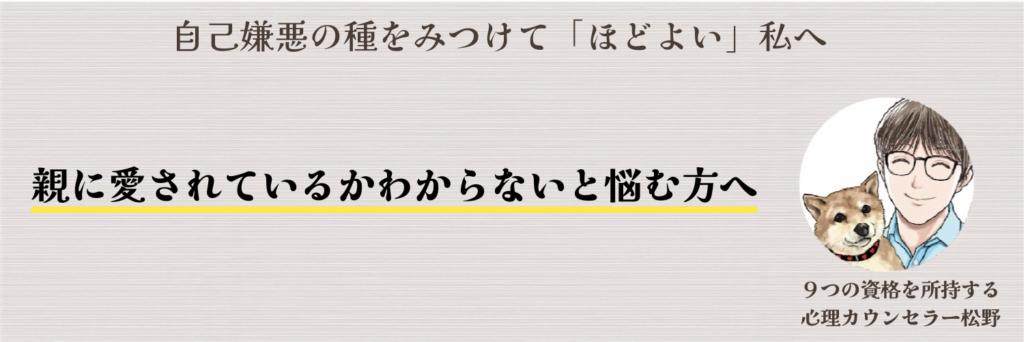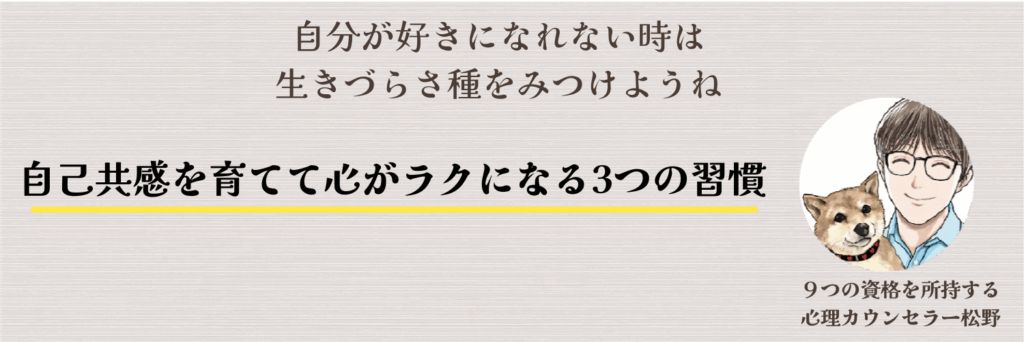
生きづらさを手放す心理カウンセラーの松野です
なぜ他人にわかってほしいと思ってしまうのか?
今日はそんなお話です。
「誰かにわかってもらえないとつらい」
そんな気持ちを抱えること、ありませんか?
たとえば・・・
・職場で頑張っているのに、誰も気づいてくれない
・家族に悩みを話しても、否定されてしまった
・「わかるよ」の一言をずっと待っている
こうした経験が積み重なると、
「自分って何なんだろう」
「私の気持ちは、どこにも居場所がない」と、
心がどんどん苦しくなってしまいます。
そんなときに必要なのが
「自己共感」という考え方です。
自分の感情にやさしく寄り添う
“3つの習慣”をご紹介していきます。
他者共感と自己共感のちがいとは?
「共感」という言葉は、
人とのつながりを深めるために
とても大切なもの。
ですが、それが“他人ありき”に
なってしまうと、
振り回されてしまう危険もあります。
他者共感:他人が自分の気持ちを理解してくれること
自己共感:自分自身の気持ちに、自分が気づいてあげること
自己共感は、心の中にもうひとりの自分がいて
「大丈夫だよ、その気持ちわかるよ」と
寄り添ってくれるような状態です。
外からの承認ではなく、
自分で自分を承認する力こそが、
揺るがない心の土台になります。
自己共感ができない人の特徴
もしあなたが「自分を共感してあげるって
どういうこと?」
「正直、自分に寄り添うって難しい」
と感じるなら、以下のような傾向があるかもしれません。
つい自分を責めてしまう
ネガティブな感情を否定したくなる
周囲の期待に応えなきゃと無理してしまう
「ちゃんとしなきゃ」が口グセになっている
こうした傾向は、過去の育ち方や環境の影響で
「自分の気持ちは後回し」が当たり前になってきた
結果かもしれません。
でも安心してください。自己共感の力は、
日々の小さな習慣から育て直すことができます。
自己共感を育てる3つの習慣
ここからは、自己共感をやさしく育てていく
3つのステップをご紹介します。
どれも特別なスキルや道具は必要ありません。
【習慣①】朝の「3つの問いかけ」
朝、まだ静かな時間。目を覚ましたあと、
次の質問を自分にしてみてください。
今、私はどんな気持ち?
その感情は、何から来てる?
今の私に、かけてあげたい言葉は?
たとえば「なんとなく不安」と感じたら、
「あ、昨日のLINEが返ってこないのが
気になってたんだ」と気づき、
「大丈夫、深呼吸していこう」と自分に声をかけてあげる。
それだけで心は少し落ち着き、
軸が戻ってくる感覚があります。
【習慣②】日中の「共感日記」
日中のすき間時間や、夜寝る前などに
「共感日記」を書いてみましょう。
スマホでも、紙のノートでもOKです。
以下のようにシンプルに書き出すだけでOKです。
今日うれしかったこと
今日しんどかったこと
その時の自分にかけたい言葉
この日記の目的は“自分の気持ちに気づく”こと。
例えるなら、心の掃除です。
心の中に溜まったモヤモヤを、
言葉にしてあげるだけで、
驚くほどすっきりしますよ。
【習慣③】夜の「小さな肯定ルーチン」
一日の終わりに、自分に声をかけてあげる
時間を作ってみましょう。
「今日もよくやったね」
「疲れてたのに、頑張った」
「ありがとう、私」
「うまくいかなくても、それでもいいよ」
この習慣は、心に“安心の居場所”を
作っていく効果があります。
最初はむずかゆくても、続けるうちに自然と、
自分への信頼が育っていくのを感じられるようになります。
自己共感が育つと、こんな変化が起きる
自己共感の力が育ってくると、
他人の言葉や態度に過剰に
反応しなくなってきます。
他人の機嫌に振り回されなくなる
落ち込んでも回復が早くなる
「私はこれでいい」と思える軸ができてくる
たとえば、以前なら誰かに否定されただけで
一日中気にしていた…
そんな人でも、「でも私はちゃんと
自分を大切にした」と思えるようになってきます。
他人に左右されず、“自分と手をつないで生きていく”。
その感覚が、人生の土台になります。
自己共感を育てるのは“心の筋トレ”
自己共感とは、「自分が自分の一番の
理解者になること」。
それは、自分の弱さも未熟さも、
まるごと受け止めてあげる優しさです。
今回ご紹介したように・・・
朝:3つの問いかけ
昼:共感日記
夜:小さな肯定
この3つの習慣は、
どれも今すぐ始められます。
特別な才能も、心理学の知識も必要ありません。
自己共感は、心の筋トレです。焦らず、ゆっくり。
ほんの少しずつでもいいので、
自分の味方になる練習を始めてみませんか?